ボードの検査を自動化したくて、環境整備を行っています。 基板1枚ごとに手動で5ステップの操作を行っていました。 […]
カテゴリー: 未分類
しごと、やめました。
新卒から15.5年勤めていた、通信用部品メーカを辞めました。 2010年前後までは、やりたい事をやる事が出来る […]
2ch電圧源。
微小電流源を別件で試作していて、評価のために細かく設定出来る 電圧源が欲しくなったので、横道に逸れて作ってみた […]
[ 頒布 ] 頒布一覧を纏めました。
頒布物が増えてきたので、頒布物の一覧ページを作成しました。 ↓ これです。 http://www.cronos […]
ボトムパッド付きQFN部品。
最近頒布しているボードに、やたら小さい部品が載っているじゃない? あれ、QFN(Quad Flatpack N […]
[ 電子負荷 ] 困った問題。
困った。 精度高く電流制御が出来て、電流モニタも出来たまでは良かったのだけど 端子電圧の測定値に誤差が出てしま […]
半田めっき線 0.5mmφ 分割頒布
半田めっき線が欲しい。 どこのご家庭にもあるTA(スズメッキ線)は、半田付けする際 半田の乗りが悪く、私も毎 […]
[ RTOS ] freeRTOS @ AVR検討
前回までで、機能としては完成したんだが 計時し始めると、どんどん時刻がズレていく問題が見つかった。 最初はオシ […]
[ Nixie ] 基板が来た。
基板が来た。 細かい所を見るとちょっと残念な点(シルクの品質とか)が有るとはいえ 自分で感光基板を焼いて作る事 […]
いやん。
困った。 モチベーションは有るし、作りたいものも決まっているんだが 時間が一瞬で過ぎちゃって何も進まない。 な […]
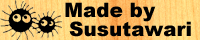 Made by Susutawari
Made by Susutawari
Comments